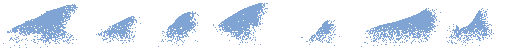
翌日。
国王が臣下の主だったものを集めた。
国王の左側には、3人の大臣。右側には、近衛隊長とふたりの将軍が並び、
それぞれの後ろには、補佐官と副官が並んでいる。
帰国の挨拶と云った所か・・・
今回の旅も国王の思いつきで、始まったことだった。
他国の見聞と剣の修行・・・同行するメンバーも国王が決めた。
アイサム、ベルメール、エンシス。
皆、剣術の腕前は確かだ。
アイサムは経済に、ベルメールは医術に、エンシスは天文に詳しい。
今度の旅でも、それは大いに役立った。
大臣、将軍から、他国の実情についていくつか質問が出た後、
国王が口を開いた。
「剣の腕は上がったか?」
「それなりに・・・です」
「ふん、それなりか・・・では、剣術大会でも開くとするか」
「それは面白そうで御座いますな」
賛同の声が各将軍から上がる。
「慌てるな。今回は若い者だけだ」
国王が制す。
1週間後。
国王の声に、この闘技場に1000人程の若者が国中から集まった。
闘技場は、城からやや離れたところにあり、古く、所々崩れかかっている。
天気はいい。
空を見上げると、青い空に秋の到来を告げるような雲が。
天から見れば、人がやっていることなどばかげたことに見えるのだろうなあ。
そんなことを思いながら、地上に視点を移す。
中には、他国の賞金稼ぎみたいなのも混じっていそうだ。
こんな大会は、年に1,2度行われるのだが・・・参加するのは初めてだ。
観客席を見ると、観客も結構多い。
この国での娯楽自体が少ないせいもあるのだろうが。
試合が始まる。
100組くらいの試合が同時に進行する。負ければ、それまでだ。
しばらく、試合を眺めていて、思った・・・使えるのは100名ぐらいか。
勝ち進むにつれて、だんだん手強くなっていく。疲れも、たまっていく。
勝ち残ってきたのは、やはり、サイアムだった。
・・・やはり、最後まで残ったか・・・。
剣を握る手が汗ばむ。
にらみ合いが続く。
黒い髪に、黒の瞳。奴の芯の強さみたいなのがヒシヒシと伝わってくる。
おかっぱ髪が風にサラサラと揺れている。
奴の腕が、ピクッと動いたかと思うと、剣が空を切る。
奴の剣を避けながら、その剣を薙ぎ払う。
次の瞬間、甲高い音とともに、奴の剣が飛んでゆく。
一瞬、呆然とする奴の顔を認めた。
「王子が優勝とはな・・・家臣共も情けないのう・・・だが、そんな細身の剣が
戦場で役に立つと思うか?剣は力だ」
突然、国王が、携えていた剣を抜き、振りかぶる。
咄嗟に、持っていた剣で国王の剣を受け流し、反す剣で国王の胸元に
・・・一瞬のことだった。
「失礼致しました」
慌てて、剣を鞘に戻し、跪く。
父であっても、国王に剣を向けるとは・・・
「わははは・・・良くやった。今日参加したものの中から、200名の近衛兵を
選ぶが良い。これは褒美だ」
豪快に、国王が言い放つ。
「王っ、そ、それは・・・」
傍にいた大臣から、戸惑いの声が。
城へ戻ると心配顔のオリエットが待っていた。
「王子様・・・」
闘技場でのことは、もう知っているのだろう。
「大丈夫だ・・・だが、まだ、手が痺れてるよ・・・」
王の一撃は強烈だった・・・。
「心配するな・・・それより、何か用があったのでは」
「あ・・・お腹が空いたんじゃないかと・・・お食事を作りました」
「オリエがぁ?」
「・・・」
オリエットの頬がみるみる膨れていく。
し、しまった。これには焦る。
「あ・・・冗談だ、オリエ。機嫌直せ」
「知りません・・・お食事は、サイアム様に、差し上げます」
「・・・な〜んだ、最初から、そのつもりだったのか」
今度は、オリエットが焦る番だった。
「ち、違います」
「どっちにしろ、サイアムの分も用意してあるんだろう?話もあるし、
呼んできてくれ」
オリエットが、未だ、何か言いたげにしている。
「どうした?」
「はい・・・あ、あの・・・後で、あれを弾いてくれますか」
「そうだな・・・オリエの料理の腕しだいってところかな」
「お呼びですか」
黒い髪が一礼する。
「ああ・・・まあ、座れ」
「それは、出来ません。王族と一緒に座るなど・・・」
「何を言ってるんだ?旅の時は一緒に座ってたじゃないか」
「あの時は、あの時・・・今は、今です・・・」
「相変わらず、固いな・・・旅で解ったはずだろう?そーゆーのは、
その土地の慣習なんだって・・・」
「それは、そうですが・・・慣習が悪いことばかりとは限りません」
「解った、解った。だが、立ったままでは食事も出来まい?兎に角、座れ」
しぶしぶと云った様子で、椅子に腰掛ける。
「今日は、手をぬいたな?」
「そんなことしません・・・」
「そうか?」
声を低くして続ける。
「ところで、今日の褒美は、異常だと思わないか?」
「・・・」
「ふたりだけだ。遠慮はいらない」
「ええ・・・褒美にしても、200名は、多すぎます。精々20名か、30名が
妥当なところでしょう」
サイアムも小声で返してくる。
「大臣達も慌てていた」
「ええ、経済的にもおかしいと言えます」
この国で近衛兵といえば、職業軍人といえる。つまり、専業ということ。
将軍配下の騎士団だって、家業を持っている。幾つかのグループに別れ、
交代で騎士団を構成している。
「200名ですか・・・」
「父上の近衛兵500名なら、砦のひとつくらい簡単に落とすぞ」
「ええ、それを考えると、国王は戦を考えておられるのかも・・・」
「父上は、各方面の情報は頻繁にとっている様だし・・・内か外か・・・」
「・・・」
少し、顔を背けるようにして、サイアスが言う。
「今回は国王の機嫌が良かったから問題なかったものの・・・
気をつけてください・・・」
トントン
「失礼しま〜す」
明るい声とともに、オリエットが食事を運んできた。
オリエットが、ワゴンからテーブルへ食事を移し始める。
給仕係りと一緒かと思ったが、違うらしい。
「ん、一人か?」
「はい・・・普通の家では、一人でするのが普通なんですよ」
「あれ、オリエの分は持って来なかったのか?」
テーブルへは、ふたり分の食事が並べられただけだった。
「え、私などが一緒に・・・」
「ないのか?ないのなら、半分分けてやるぞ」
「い、いえ、あります・・・けど・・・良いのですか?」
「早く持って来い。アイサムが旅の話をしてくれるぞ。なっ」
「え、ええ・・・」
アイサムが頷く。
「はい。すぐに用意して来ます」
オリエットが転がるように廊下へ飛び出していく。
見ていて、可笑しいくらいだ。
前とちっとも変わっていない・・・
「そこで、だ・・・200名を選ぶのを手伝って欲しい」
「はあ・・・」
「なんだ・・・気乗りしない返事だな」
「ええ・・・私に任せ切りになるのは見えてますから・・・」
「察しがいいな・・・」
「・・・」
オリエットが、ワゴンを押してくる気配がする。
数秒して、予想通り、戸が開き、オリエットが部屋に入って来た。
3人の食事が、テーブルに並び、オリ絵が席に着く。
「オリエ、お土産のお礼を言いたかったんじゃないのか?」
「はい。サイアム様、有難う御座いました」
「私は別に・・・何もしていません」
「いや、オリエへの土産だと言ったら、張り切って節約してたぞ」
「そ、そんな・・・」
サイアムの頬が少し赤みを帯びる。
「さて、オリエの作った食事を頂くとするか」
「これを、オリエット様が・・・」
「ん、お腹をこわさないか、心配なのか?・・・大丈夫そうだぞ」
「ち、違います」
「サイアム様、いつも、こうなんです・・・気にしないで下さい」
と、オリエは軽く受け流す。
「はい・・・嫌と言うほど、解ってます」
「お前等なあ・・・それより、中央の国ベルフィールージュの話は、どうだ?」
「そうですね・・・」
・・・
「今日は、このくらいで・・・」
「サイアム様、有難う御座います。私も行ってみたくなりました」
「サイアム殿」
「これは・・・大臣」
「王子様のご用件は?」
「は・・・」
「お呼ばれになられたのでしょう?」
「あ、ええ、オリエット様がお土産のお礼を言いたいからと・・・
それに、旅の土産話等を少し・・・その機会を作ってくださったようです」
「・・・」
オリエットの料理は美味しかった。
約束通り、あれ・・・ハープを弾くことになる。
「いつ聴いても、優しい音です」
「そうだな・・・旅に出る前だったかな?前に弾いたのは・・・」
「はい」
「自分で弾けるようになったらどうなんだ」
「私は聴いているほうがいいです・・・」
「・・・」
時々、船が難破し東の海岸に打ち上げられることがある。
これは、その時の戦利品だ。
この国では、楽器などに、誰も興味を持たない。
オリエットが・・・打ち捨てられようとしていたのを、ここへ運び込んだという訳だ。
国王は、案の定、捨てるようにと言ったが、オリエットが頑張った・・・
と言うべきか。
このときばかりは国王が折れた。
それでも、自分で弾くのかと思えば、人に弾かせて・・・
今では、王子を辞めても吟遊詩人とかでも、やっていけそうだ。
第1話 終了
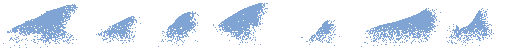
★ NOVEL TOP ★ BACK ★ NEXT ★